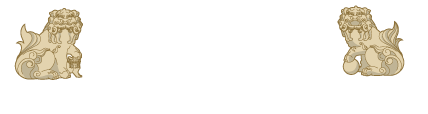古楽夢 ~五拾九~

木曾海道六拾九次之内
垂井/広重画
広重は雨がそぼ降る中を西から垂井宿へ入ろうとしている大名行列を真正面からとらえている。松並木の連なる中山道が垂井宿へ入りかけた所の両側に、石垣の上に土塁を築いた門のようなものが見えている。これを見付といい、城の城門を真似て宿場の入口に設けたものである。羽織袴の宿役人が傘を差してここまで出迎えにきている。一方行列の先頭を切って、蓑を着た先払いの2人が竹の杖を持って「したぁにー したぁにー」と唱えながら見付を入ってくる。さらにその後には、もう陸尺(駕籠舁)に担がれた乗物(大名の乗る駕籠)が現われている。松の幹と幹との間には中間の持つ槍も頭を出している。先払いの声に急かされて、街道の右側の茶屋では主人と荷物を天秤で運ぶ蓑を着た人足が、また左側では赤合羽を着た旅人と茶屋の主人が、いずれも茶屋の外で土下座して行列を迎えている。右側の茶店には「御休処」の看板が雨を避けて家の中の壁に立てかけてある。その壁に遊女や風景の浮世絵が掛かっている。他方左側の山形に林(版元錦樹堂の商標)の紋を掲げた茶店では旅人に「おちゃ漬」を出すばかりでなく、浮世絵も壁に掛けて売捌いている。いずれも、版元錦樹堂が浮世絵の販売に深い関心があったことを示している。
江戸時代の手鏡

ケース 表面 裏面
昔々は、鏡は呪術用の道具使われていたほど神聖なものでした。歴代の天皇が受け継いできたという宝物、 有名な『3種の神器』というのも、剣に勾玉、そして鏡なのです。もちろん技術的にはいまほど美しく磨かれてなく、 ぼんやりと姿が映る程度だったとしても、やはり、自分の姿が映る鏡に不思議な力が備わっていると考えても当然でしょう。 そんな神聖なものだった鏡も、平安~室町、そして江戸時代へと時代を経ていくにつれ、お化粧道具として大衆の文化の中に溶け込んでいきました。 手鏡という形に変化していったのも、室町時代以降のことだとか。

『江戸名所図解』
四谷内藤新駅(部分)三研ぎ
写真右下:
鏡(木の蓋をかぶせた状態)
戦乱の時代が過ぎ、平和な江戸時代に落ち着くと、文化も成熟していき、女性たちの美への関心もますます高まっていきます。 江戸時代になってくると、庶民もごくふつうに手鏡を持つようになってきました。 江戸時代には、結い髪も面白く複雑になっていきましたし、頬紅が流行したことなどもあって、女性たちはどんどん『装う』ことに熱中していったのでしょう。 この時代の鏡は、長く使っていると曇りやすくなっていったので、家々の鏡を研いでまわる鏡研ぎ職人なんていう職業も登場します。 やっぱりお洒落に鏡は欠かせないものですから、メンテナンスも必要だったのでしょう。鏡ってまさに時代を映す鏡なんですね。
江戸散策より抜粋